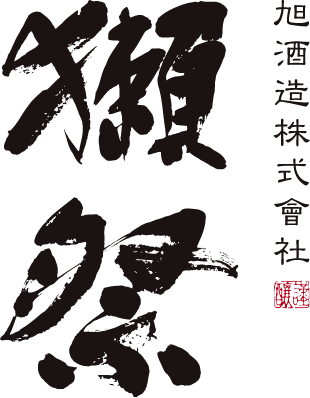「獺祭は売り上げ一千億円に挑戦する」と話しています。この金額は世界のシャンパンやワイン、果てはファッションまで含めて、ラグジュアリー市場の一角を占めようとするとき、最小限このぐらいの売り上げボリュームがなければ、世界において、存在感はないだろうという目算から出てきた数字です。
先日、ある社員から「今、世界の酒の小売りの現場で見ていると、日本のウィスキーなど蒸留酒がブームです」「うちも蒸留酒の分野を強化して、そちらを主体として開発して、この流れに乗っていくほうが、一千億を目指す時、良いのでは」という意見が出てきました。これはマーケティングという観点から見る時もっともな意見です。まず、目標を設定して、しかる後にその目標にどうしたら効率よく到達できるか戦略と手段を考える、まさに正論なのです。うちがどこかのコンサルタント会社に依頼していれば必ずこの意見が出ると思います。
しかし、私の答えは「否」でした。
蒸留酒といえば、獺祭焼酎も造っていて、これはこれで大事な商品として売ってきましたし、品質についても少しでも向上させるべく改善と改革を繰り返してきました。また、焼酎に持っていけない上槽酒の残酒などの救済策としてジンやその他のリキュールも研究しています。しかし、それらはどこまで行っても「清酒」としての獺祭に付随するものとして考えてきました。獺祭は清酒としての獺祭が中心にあってそれに従うような形で獺祭焼酎などの製品が同じイメージのもとに集まっている。そしてそれらの「清酒」以外の製品はあくまで獺祭の生産を助けるためや大切な山田錦を無駄にしない目的のもとにあり、決して「売らんかな」が最初に来るのではない。そしてもちろん、商品としてのイメージも「獺祭らしい」ものでなければならない。
ただ短期の売り上げとしてみた場合、私の考え方は不利なのは十分承知しています。しかし、長期的に見た時、「これで良いんだ」とも考えております。商品の多角化を推し進めるほうが一千億に早く到達する可能性は高いと思います。しかし、そのとき獺祭というブランドはスカスカになっていることでしょう。毎日、相当な高い目標に応えて努力しているスタッフたちを見ていると、なるべく早く効率よく目標値に到達することが正解に思えますが、それでも試行錯誤しながら一千億を目指すのは「獺祭というブランドの幹を太くしながら伸ばしていかないと、本質的な成長につながらない」、こんな思いがあるからです。
☆人件費バランス☆
獺祭は2025年時点で販売量が日本で11番目、販売金額が3番目、製造スタッフの数は200名以上パートさんなど入れれば300名近くで、二位に倍以上の差をつけて断トツ日本で一番です。そして、少なくとも酒造業界において給与水準はこれも日本一。つまり売り上げと人件費のバランスが取れていない。というより取ろうとしない、経営学の常識から逸脱している経営を続けています。
いかにも「甘っちょろく青臭い経営」に見えることと思われます。しかし、この甘っちょろくて青臭さが獺祭からなくなったら獺祭ではない。こんな獺祭を「山口の山奥の小さな酒蔵」からここまで押し上げてくれた「奇跡のようなお客様たち」に感謝しています。
あの酒販業界の第一人者とだれもが思う「はせがわ酒店」の長谷川社長に、「獺祭を見ていると、奇跡ってあるんだなあ・・・と思う」と、あるパーティーの席上で語っていただきました。
ところで、この獺祭が海外において苦労しているのはこのあたりの考え方が国によってはうまくかみ合わないことです。外国はマネー!マネー!マネー!!!の国もあれば、マーケティング!マーケティング!マーケティング!!!の国もあります。苦労してます。こんな弱音を吐いているとユニクロの柳井社長からは、「それはあんたが良い外国人と出会ってないからだよ」「外国人にも良いのと悪いのがいるよ」と笑われるんでしょうが。良い外国人の人脈を作り、その国の社会に無自覚に合わせるのではなく、獺祭の良いところを表現しながら発展できるよう努力します。